|
【経営内容を示して社員の理解を得たA社】
経営状態が思わしくなく、賞与の支給も危うかったとき、A社長は社員を集めて「今期は業績が厳しいため、夏冬の賞与は支給できそうもない。決算終了後に利益が出た 場合にその分を決算賞与として全員に支給するから、頑張って欲しい」と、自社の経営内容等を示して訴えた。これには、社員も納得して、利益を出すために、また会社 の将来も考えて働いた。結果、利益を出すことができ決算賞与を支給できたという。また社員の頑張りから業績も上向きになりつつあったため、翌年からは、従来の夏冬型の賞与に戻した。 |
|
【少ない原資から支給してヤル気を起こさせたB社】
B社は業績が低迷し、賞与の支給原資がほとんどなかった。しかしB社長は「賞与を支払えないのでは、社員に申し訳ない」と考え、社長の報酬を減額するなど何とかやりくりし、少額ではあったが成果に応じて支給した。賞与は出ないと思っていた社員は、社長の思いに感激し、ヤル気を起こし業績も徐々によくなりつつあるという。 |
賞与の原資が確保しにくい厳しい時代ではありますが、このように経営者の姿勢や賞与の支給方法によっては、社員のヤル気もずいぶん違ってくるようです。 |
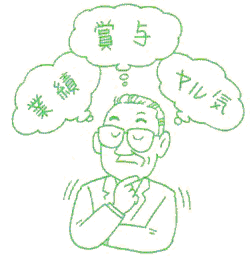 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
