

|
 賃金は生活に直結した問題 賃金は生活に直結した問題
|
最近、新聞紙上で大企業の賃下げのニュースがよく見かけられます。すべての分野での改革が求められるなか、賃金もまた今までにない変革が求められ、賃下げという初体験を経験する企業も珍しくない状況です。ところが賃金は従業員にとって生活に直結した問題であり、労使協定や賃金規程、個別の労働契約など形態はさまざまですが、いずれも労働契約上すでに決められているものです。それにもかかわらず賃下げをしなければ企業の存続すら危ない場合に、どのような条件を満たすことによって賃下げができるのでしょうか。
法的な問題を考慮せずに賃下げを行い訴訟に発展するケースが見られますので、慎重に行わなければなりません。
|
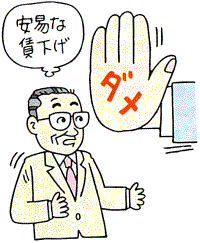
|
|
 賃下げの事例 賃下げの事例
|
賃下げの実施について、次のような事例があります。
|
【長野県の場合】
|
|
今年度から3年間、県職員の給与を5~10%削減する。部長級10%、課長級8%、一般職6%、若手職員5%の削減となっている。
|
|
【東京都A市の場合】
|
|
平成13年に、A市は財政難を理由に臨時的に全職員の賃金カットを発表した。その内容は、係長以上部長までが2%、主任以下は1.5%の削減となった。
|
|
【運送業B社の場合】
|
|
B社は、役員10%、課長以上の管理職5%、一般社員は3%のカットを行った。
|
|
 賃下げの前提条件とは? 賃下げの前提条件とは?
|
|
賃下げを行う前に、次の事項を充分検討しましょう。
|
|
〔前提条件1:回避の努力をしたか〕
|
|
企業としてあえて賃下げを選択するには、まず第一に、企業が経営面で、そのような事態を回避するための努力をどれだけ払ってきたのかということが問われます。仮に回避努力が払われていなかったり、不十分であれば、従業員の賃金減額に踏み切る前に、経営の再建に向けてあらゆる努力を行うことが優先されるべきです。そうでなければ経営者による権利の濫用となります。
|
|
〔前提条件2:事情説明あるいは話し合い、事前協議を充分にしたか〕
|
|
賃下げに踏み切らざるを得なくなった事情や、賃下げの方法などについて従業員に懇切丁寧な説明を行い、同意を得ることが大切です。その過程で話し合いの場をもち、労働組合がある場合は事前協議を行うことなどが必要になってきます。
|
|
〔前提条件3:賞与の減額または不支給をしているか〕
|
|
月例給与とは異なり、企業の経営実績あるいは従業員本人の業務実績を基準にする賞与の減額等を先に行うのが常識です。
|
 賃金の引下げのプロセス 賃金の引下げのプロセス
|
|
次のような手順が考えられます。
|
|
ステップ①
|
役員報酬を減額、次いで管理職の賃下げの内容を重くする
|
|
|
賃下げの状態を作った経営上の責任として、まず役員報酬に手をつけるのが常識です。さらに従業員の中でも賃金の額が高く職務上の権限も重い管理職について、一般社員よりも賃下げの内容を重くすることが必要です。
|
|
|
|
各種手当の中には、従来の慣行で必然性の薄い手当やそれほど生活に深刻に影響しない手当があるとすれば、そうした手当から合理化すべきでしょう。
|
|
|
基本給の減額は、最後に行うべきです。その場合、「一律○%減額」というやり方が通例ですが、「○年間」というように期限をつけて実施されることが多く、その方がよいようです。というのも、賃下げの結果、従業員が遠い将来にまで希望を失ってしまっては元も子もなくなるからです。
*月例給与と賞与を含めて「年収の○%カット」というやり方もありますが、方法についてはよく検討する必要があります。
|
 高齢者だけの賃金カットは可能か? 高齢者だけの賃金カットは可能か?
|
多くの企業は、若年者ではなく特に勤務年数の長い社員の賃金について矛盾を感じ、手をつけることが必要だと思っているようです。例えば、全従業員というよりも高齢者だけを対象とした賃金の減額は可能なのでしょうか。その場合は、次の条件が必要と考えられます。
(1)代償措置がある
例えば、雇用延長といった代償措置があるときです。
(2)不利益の程度が大きくない
賃下げの程度がそれほど大きくないときです。
(3)職務職責の軽減を伴っている
職務や責任を軽くした場合、それに伴って当然それに見合う賃金に減額するときです。
|
*60歳時に比べて賃金が15%を超えて下がった場合に65歳未満の人の賃金を補てんする「高年齢雇用継続給付」の利用も検討しましょう。(5月から支給要件等変更の可能性があります・問い合わせは「ハローワーク」)
|
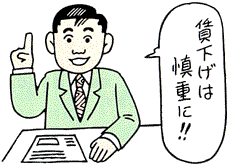
|


|