

|
企業は日々の活動のなかで、取引先から証ひょう書類を受け取り、さまざまな書類を作成しています。ところで、こうした書類等はきちんと整理保存しているでしょうか?
|
 【帳簿書類等を保存していないと面倒なことに】
【帳簿書類等を保存していないと面倒なことに】
|
帳簿書類などを保存していないと、経営においても、また税務調査においてもさまざまな支障が予想されます。
保存すべき書類等を誤って捨てた場合など、面倒なことになります。
|
事例:
A社は、決算が終わったこともあり、また過去の領収書などの証ひょう書類
や帳簿書類などが倉庫の場所を占めているために整理を行った。その際、保存
しておかなければならない書類の一部を誤って処分してしまった。
こうした書類等は経営上の重要なデータであるため、過去の実績との比較をす
る際や経営計画策定の際、非常に困ったそうだ。またその後、税務調査が行な
われることになったが、取引の根拠となる証ひょう書類や帳簿などが部分的にな
いことからきちんと説明できなかったという。
|
|
*消費税法では、仕入税額控除を受ける要件として、帳簿および請求書等の保存
が義務づけられています。この「帳簿および請求書等の保存」とは単に物理的に
どこかに保存しているだけではダメなようです。つまり税務調査等の時にすぐに
提示できる状態で保存しておかなければなりません。仮りに税務調査の際の再
三の提示要請にもかかわらず、提示を拒むと仕入税額控除が受けられないこと
もあり得ます。
|
|
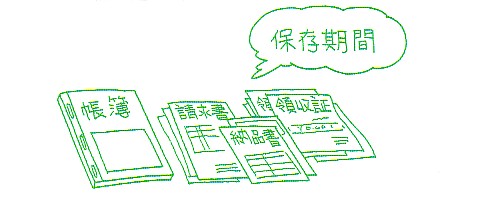 |
 【保存期間が決められている書類がある】
【保存期間が決められている書類がある】 |
企業活動に伴う書類は、処分していかないと増えるばかりですが、だからといって何でも捨てていいということではありません。
企業には、法律で保存期間が定められている書類や、法律で定められていなくても重要度が高く保存しておかなくてはならない書類があります。こうした書類は帳簿書類保存箱などにきちんと整理し、書類管理ノート等を作成して、必要なときにすぐ取り出せる状態にしておかなければなりません。
|
<電子データでも保存ができる?>
|
所得税法や法人税法等で保存しなければならない帳簿書類のうち、コンピュータで作成するものについては、税務署長の承認を受けた場合、一定の要件のもとで、コンパクトディスクや磁気ディスクなどの媒体に記録した電子データのまま保存できます。
[電子データによる保存が可能な帳簿書類]
自己が最初の段階から一貫してコンピュータを使用して作成する帳簿書類で、次のようなものが対象となります。
・ 仕訳帳や総勘定元帳、補助元帳等の帳簿
・ 貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類
・ コンピュータで作成し、相手方に交付する請求書や領収証等の控え など |
|
 【帳簿書類等はいつまで保存すればいいのか?】
【帳簿書類等はいつまで保存すればいいのか?】
|
税務上の帳簿書類については、法律で7年間ないしは5年間の保存が義務づけられているものがあります。(表1参照)
これらの保存場所は、納税地(通常は本店所在地)または支社、営業所と税法で規定されています。
*商法でも書類の保存が決められています。
例えば
・ 定款や株主名簿は備えておくことが定められています。
・ 株主総会議事録や取締役会議事録は10年間保存しなければなりません。 |
 |
<表1:帳簿書類などの税務上の保存期間> |
| 種 類 |
例 示 |
保存期間 |
| 一切の取引に関する帳簿 |
仕訳帳、現金出納帳,売掛帳,買掛帳、固定資産台帳など |
7年 |
| 決算に関する書類 |
たな卸表、貸借対照表、損益計算書など
*商業帳簿および営業に関する重要書類(貸借対照表や損益計算書、営業報告書、利益処分案、各付属明細書、総勘定元帳など)は
商法により10年間保存 |
| 現金の収受・支払い、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引書類 |
領収証、預金通帳、借用証など |
| 有価証券の取引に際して作成された書類 |
有価証券受渡計算書、有価証券預り証など |
| たな卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類 |
納品書や送り状など |
5年 |
| たな卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類以外の書類 |
請求書や見積書など
* 資本金1億円超の大法人は7年
* 国外取引に関するものは6年 |
|
《注意》消費税法では,仕入税額控除を受けるためには、帳簿および請求書等の両方を7年間保存しなければなりません。ただし6年目および7年目については、帳簿または請求書等のいずれかの保存でよいことになっています。 |
[an error occurred while processing this directive]