

|
売上がなかなか伸びない状況なので、販売活動に力を入れなくてはなりませんが、せっかく販売してもきちんと代金を回収できないと売掛金(債権)が増えて経営を圧迫します。債権回収を滞らせないためにはどうしたらいいのでしょうか。
|
 【債権回収の心得】
【債権回収の心得】
|
|
債権回収に妙手はないともいわれています。つまりは、オーソドックスな対策で、泥臭くかつ着実に行うことが重要なようです。ただし、その際のポイントは次の点です。
|
|
《債権回収の3つのポイント》
|
|
①社長は情に流されない姿勢を示す
|
|
例えば、得意先の社長から手形のジャンプなどの依頼がきたとき、情に流されてすぐ受けていませんか。まず「売掛金はきちんと回収する」という社長の強い姿勢が重要です。同時に社長は、債権残高を常に把握しておかなければなりません。
|
|
②金にはうるさい会社だと取引先に思わせる
|
集金日に行かなかったり、入金が遅れてもそのままにしていると、だんだん支払が後回しにされていきます。次のような対応で、いい加減なことはできないという印象を与えましょう。
・支払日の前日には確認の電話を入れる。
・入金予定日に少しでも遅れたときや内金になったときは即連絡をとり理由を聞く
・現金・小切手での支払が手形に変わったときには理由を相手に確認する など
|
|
③迅速に対応する
|
|
クレームや返品・値引き処理は速やかに行わなければなりません。また、支払いについて、相手先に変化があった場合も素早く対応します。回収はタイミングが重要です。時機を逸することなく迅速に対応しましょう。
|
 【こんな方法で効果を上げている】
【こんな方法で効果を上げている】
|
|
債権回収にはどの会社も苦労しているようですが、なかには工夫して効果を上げている会社もあります。
|
|
事例1:
|
未収金の早期把握・早期回収を徹底しているA社
|
|
|
卸売業のA社は、次のことを徹底して効果を上げています。
|
|
①
|
未収金の早期把握
|
|
|
|
月ごとに担当者別・得意先別の未収金を一覧表にして把握する。
|
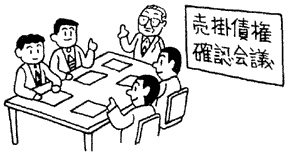
|
|
②
|
未収金の発表
|
|
|
毎月、未収状況を社員全員に発表する。
|
|
③
|
担当者が対策案を考え上司と検討
|
|
早期の行動のため具体策を検討する。
|
|
④
|
具体策に基づき早期に催促
|
|
事例2:
|
社長・幹部社員も回収に乗り出し全社で取り組むB社
|
|
|
製造業のB社は、売掛金の早期回収に全社をあげて取り組んでいます。 まず担当者別・得意先別の債権一覧表(滞っている債権も含めて)を作成し、入金があればその都度更新します。 この一覧表に基づいて担当者一人ひとりから個別に状況を確認し、その状況次第では内容証明郵便を送った後に訪問するなどきめ細かく対応しています。 ケースによっては、担当者だけに任せるのではなく、幹部社員や社長自らが回収に足を運んで確実に回収しています。
|
|
 【債権回収に向けた具体策】
【債権回収に向けた具体策】
|
|
債権をきちんと回収する方策として、次のようなことが考えられます。
|
|
具体策①
|
得意先別に債権を管理する
|
|
パソコン等を使って、担当者別・得意先別に売掛債権を管理する。入金予定日や入金方法等も明示し、少額の未入金もリアルタイムにこまめに把握する。
|
|
具体策②
|
毎月初めに売掛債権確認会議を開催する
|
|
営業担当、経理担当等を集めて毎月初め「売掛債権確認会議」(仮称)を開催し、売掛債権回収の重要性を認識させ、個別的に回収の進め方等を合理的に話し合い、各人別に回収目標を決めて実行させる。
|
|
具体策③
|
振込入金から訪問による集金への切り替えも検討する
|
|
振込入金が遅れがちな場合は、訪問による集金に切り替える。なお全額回収が不可能な場合は、分割でも定期的に回収する。
|
|
具体策④
|
残高確認書を送付する
|
|
年1回は残高確認書を得意先に送付し、自社の売掛金残高に間違いがないか確認してもらいましょう。差異が生じた場合は、原因を確認し最終的には一致させておきましょう。
|
|
具体策⑤
|
長期に滞っている債権は内容証明郵便の送付などを検討する
|
電話や訪問による督促でも回収できない場合は、「内容証明郵便」や「少額訴訟制度」の活用を検討しましょう。
*少額訴訟制度は30万円以下の金銭支払請求事件を迅速に解決するための裁判制度です。簡易裁判所での審理は原則的に1回で終わり、審理当日に判決が下ります。
|
|